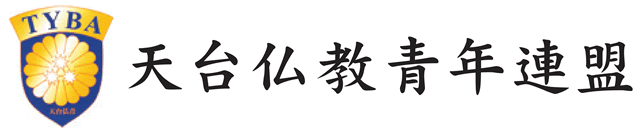過去、お寄せいただきましたご質問から内容をまとめましていくつかを掲載させて頂いております。
ご質問にたいしての返答は各地区の青年僧が回答しておりますので、地域によってはあてはまらない事や習慣の違い、天台教学と完全一致した内容でない場合もございます。
青年僧らしい返答のため、なにとぞ、その点をご理解いただきたいと思います。
Q 祈りはかなうのでしょうか。お坊さんはどう思いますか?
私たちは、与えられた一生の中で数多くの希望や困難に出会って生きています。このことは、すでに皆さんも経験したことがあることでしょう。そのような時に、「何かにすがりたい」と感じたことはありませんか?これこそが「祈り」に結びつく心だと思います。
日常の生活の中で、自分の力だけではどうすることもできない物事に対し、それを乗り越えるため「目には見えない大いなる何か」に畏敬の念をはらうことで力を頂き、自らの背中を押してもらう。これこそが祈りの基本なのかもしれません。
このときの「大いなる何か」が、私たち仏教徒であれば仏さまであり、キリスト教であればイエスさまであるのです。
しかしながら、「祈り」という行為が希望をかなえ、また困難を乗り越えさせてくれるかは、私たち自分自身にかかっているということを忘れてはなりません。日常から何かを成し遂げようとする強い心を持って生活し、自身が努力した結果に対し、さらに力をお与えくださるのが仏さまなのです。
困った時だけでなく、日頃から、「目には見えない大いなる何か」に畏敬の念を現し、生活してゆくことが大切なのです。
平成24年度 本山仏青 回答
Q お坊さんの食事の特徴について教えてください
みなさんは「精進料理(しょうじんりょうり)」という言葉を聞いたことがあると思います。肉や魚を使わないで、野菜や豆類を中心とした食事のことです。お坊さんの食事はこの精進料理が基本となっています。
現在、精進料理の専門店では、見た目や食感がお肉やお魚に似ているのに実は大豆や山芋から作られていたりして、楽しい料理がだされますが、精進料理の本来の意味は殺生をしてはいけない、肉食をしてはいけないという仏教の戒律にあります。
生き物の命を奪うということを極力さけた食事が守られてきたということです。
しかしよく考えてみますと、命はなにも魚や動物だけでなく、植物にもありますよね。涅槃経というお経の中には「山川草木悉皆成仏(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)」と説かれ、この世に存在するあらゆるものに仏様の命が宿っているとされています。
そういう意味では、食べものすべてに命があるのですね。お坊さんに限らず、大切なのは食事の前には「いただきます」、食事の後には「ごちそうさまでした」とお唱えし、無駄な大食いや食べ残しをせず、心から命をいただくことだと思います。
今ではお坊さんも修行期間を除いて日常の生活では、現代人と同じようなものを食べている方が多いのですが、他の命をいただいて生かせてもらっているという感謝の念を、この文章をお読みの皆さんも是非お持ちいただきたいと思います。
平成24年度 滋賀仏青 回答
Q 祈祷札に期限は有るのでしょうか
そもそも祈祷とは「祈=望むところに近づきたいと神仏にいのる(・・・)」と「祷=長々と神仏に訴えていのる(・・・)」の二文字で共に神仏に対していのる(・・・)行為です。
そして御札とは「札=文字を記する為に使用する木」を意味します。よって祈祷札とは現世利益の目的達成への祈りの儀式(護摩焚きナド)を行い、その内容を記した札ということになります。
では、御札の期限とは……。例えば「家内安全」や「身体健康」は常にそうありたいので区切りはありません。「必勝祈願」や「受験合格」の場合は一つの区切りの線引も分かりやすく御札の返納・焼納もよいでしょう。しかし、「御札任せ」だけではなく努力も苦労も必要です。さらに神仏に対して感謝の気持ちを持ちましょう。
新年を迎えるにあたり、又は気分一新として新たに願掛けを行いたいなど貴方の節目(・・)が期限なのかもしれません……
平成24年度 京都仏青 回答
Q 日常のおまいりについて、どのようなことをこころがけたらよいでしょうか
天台宗では、一般に朝夕の勤行として「朝題目に夕念仏」が行われています。
「朝題目」とは、朝に法華経を唱えることによって、自らの罪を懺悔(さんげ)し、心を清らかにします。「夕念仏」とは、夕に念仏を唱えることで、ご先祖さまに感謝し、またすべてのものに感謝をすると同時に、自分の心の中にある仏さまを見つめなおします。
何かと忙しい現代、朝夕に長いお経を唱える時間もなかなか作れません。でも、心の中にいつも懺悔と感謝の気持ちを持っていれば、仏壇やお墓に手を合わせるだけでも、仏さまはあたたかい慈悲の心で包んでくださり、あなたの気持ちを毎日満たしてくれるでしょう。
平成24年度 近畿仏青 回答
Q 日常のおまいりについて、どのようなことをこころがけたらよいでしょうか
天台宗では、一般に朝夕の勤行として「朝題目に夕念仏」が行われています。
「朝題目」とは、朝に法華経を唱えることによって、自らの罪を懺悔(さんげ)し、心を清らかにします。「夕念仏」とは、夕に念仏を唱えることで、ご先祖さまに感謝し、またすべてのものに感謝をすると同時に、自分の心の中にある仏さまを見つめなおします。
何かと忙しい現代、朝夕に長いお経を唱える時間もなかなか作れません。でも、心の中にいつも懺悔と感謝の気持ちを持っていれば、仏壇やお墓に手を合わせるだけでも、仏さまはあたたかい慈悲の心で包んでくださり、あなたの気持ちを毎日満たしてくれるでしょう。
平成24年度 近畿仏青 回答
Q 出家とは、どういうことでしょうか?
天台宗では、一般に朝夕の勤行として「朝題目に夕念仏」が行われています。
「朝題目」とは、朝に法華経を唱えることによって、自らの罪を懺悔(さんげ)し、心を清らかにします。「夕念仏」とは、夕に念仏を唱えることで、ご先祖さまに感謝し、またすべてのものに感謝をすると同時に、自分の心の中にある仏さまを見つめなおします。
何かと忙しい現代、朝夕に長いお経を唱える時間もなかなか作れません。でも、心の中にいつも懺悔と感謝の気持ちを持っていれば、仏壇やお墓に手を合わせるだけでも、仏さまはあたたかい慈悲の心で包んでくださり、あなたの気持ちを毎日満たしてくれるでしょう。
平成24年度 近畿仏青 回答
Q お坊さんの戒律について教えてください
日本のお坊さんは殆ど妻帯してお酒を飲んでいるから破戒僧しかいない!と、檀家さんにたまに言われます。でも、結婚や子育て、お酒を飲んで歓談する経験なんてお坊さんには必要ない!とは言われません。
そんなわけで、やはり日本では人生の苦しみを理解し、助言出来る様な人のほうがお坊さんとして求められている様な気もします。とはいえ、仏教には種々戒律がありますが、全てを一生絶対に守り切るという事は、非常に難しいものです。ただ、慢心せずに善行に励む為には、常に意識しておく必要があるのかも知れません。
平成24年度 岡山仏青 回答
Q 仏壇のおそうじのしかたについて教えてください
(唐木部分)
・日常のお手入れは毛ばたきでほこりを落として、乾いた柔らかい布(シリコンクロス、綿布等)でから拭きして下さい。
・汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を布につけてかたく絞って汚れを落とします。その後、洗剤が残らないように水をつけた布をかたく絞って拭いて、最後に完全に水分を拭き取って下さい。
(漆塗り部分)
・毛ばたきでほこりを払ってから乾いた柔らかい布でから拭きして下さい。
・汚れがひどい場合はぬるま湯につけた布で汚れを落とし、すみやかに乾いた柔らかい布で完全に水分を拭き取って下さい。
(金箔部分)
・直接布などで拭くと、金箔がはがれおちて漆の塗り面(黒色)が露出することがあります。毛ばたきで軽く払う程度にして下さい。
(真鍮等の仏具)
・乾いた柔らかい布でから拭きして下さい。汚れがひどい場合はぬるま湯につけて優しく洗って、最後に完全に水分を拭き取って下さい。
以上、日常のお手入れについてまとめてみました。もしわからない事があれば近所の仏具店に尋ねてみて下さい。
平成24年度 山陰仏青 回答
Q お位牌や仏像の開眼供養はどうして必要なのですか?
開眼の必要なものには位牌、仏像の他に石塔(お墓)、塔婆、御札など沢山の種類があります。それぞれ多少の意味合いが変わりますが、全てお坊さんによって開眼を行うのが慣わしとなっています。一般には性根を入れるといったりしますが、元々性根とは本来正しい心、本質的なものを指します。ここでいう正しい心とは、お位牌であれば故人への供養の心、ご先祖への崇敬と感謝の心、そして仏像なら仏教に対する信仰の心といったところです。
もっとも、正しい心や信仰心などといっても、形はなく目で見る事も手で触れることも出来ません。まして現代社会では仕事に忙殺されたり、他の楽しい事に目がいったりして、目に見えない大切な心はとかく行方不明になりがちです。ですから本当に大切なものは形にして見失わないようにしなければなりません。開眼とはそうした目に見えない大切な心を形にして、見失いそうになってもまた見つけやすいように標しをつける作業なのです。お坊さんにお経を上げてもらう、花や水を備え、ろうそくを付け、線香を立てる、この行為が形のない心を顕すことで、目に見える大切なものと成りうるのです。
開眼は立ち会う人の清浄な心が一番重要なので、日常の雑事は忘れ、敬虔な気持ちで臨みましょう。
平成24年度 四国仏青 回答
Q 護摩修法のご利益について教えて下さい
護摩とは、古代インドのhoma[焼く、焚(た)くという意味の言葉]の音写からきている密教の祈祷修法の一つで、御本尊様(主に不動明王)の前に火炉のある壇を設けて、おこした火の中に木や穀物などの供物を投じて御供養をするお祈りの仏教儀式です。屋内で行われることが多いのですが、外で修される場合もあります。その中で、丸太でキャンプファイアーのように壇を組みヒノキの葉で覆い火を焚くのを「採燈護摩」といい、その燃え残った炭の上を歩く「火渡り」といった法要もあります。
そのご利益は、おこした炎を御本尊様の智慧の象徴として、むさぼり・いかり・おろかさといった人間の煩悩を焼き尽くし、様々な願いを清浄なものとして成就するよう祈願するのです。祈願の1つの形として、火にくべる木(護摩木)に願い事と名前を書いて御本尊様にお願いする「添護摩」があります。
平成24年度 九州西仏青 回答
Q 腕輪念珠をする腕って決まっているのですか
私たちにはそれぞれ利き手がありますが、腕輪念珠をする場合は左手でよろしいと思われます。
左手は「自分」を表し、右手は「仏さま・故人」を表すともいわれます。
念珠というのは仏様を身近に感じて生活するべく、自分を清浄に保つ為に持ち、自身の心を支える法具です。
仏事に限らず、腕輪念珠は左手に持ちます。「左手は自分」という意味からです。
平成24年度 九州東仏青 回答
Q ペットの死について、どのように供養したらよいですか?
人間であれ動物であれ、生命の尊さにおいて違いはありません。
動物の死を仏事で弔うという事例は、歴史上数多く見られます。例えば、家畜として飼っていた牛馬の死に対して、漁で獲った魚に対してなど、感謝の意も込めた供養は積極的に行われてきました。しかし、同じ動物でもペットとなると少々感覚は異なるでしょう。共に暮らし、家族の一員だったのでしょうから、人間と同じように供養することもあるはずです。飼い主が求める形態・頻度でご供養されるのがよいかと思います。お付き合いのあるご寺院、またペット霊園などにご相談されるのも結構でしょう。
平成24年度 東海仏青 回答
Q 御開帳って何ですか
お寺の仏様はそのまま安置されている場合もありますが、中には厨子と言う仏様を収める入れ物にお入りになって秘仏として普段は直に見られない仏様もおられます。その厨子の扉を開け仏様を直に見られるようにする事を御開帳と言います。
御開帳をするお寺は月に一度、年に一度、数十年に一度などそれぞれ間隔が違います。ちなみに長野・善光寺の前立本尊様の御開帳は七年に一度行われております。
平成24年度 信越仏青 回答
Q どうしていっぱいいろんな宗派があるのですか
みなさんは、「対機説法(たいきせっぽう)」というコトバを耳にされたことはございませんか。これはお釈迦さまの布教・教化の特徴をよくあらわした用語です。お釈迦さまはいろいろな方々に教えを説かれました。ですから、お釈迦さまは相手の宗教的能力や境遇その他諸事情、諸条件を考慮して、わかりやすく法を伝えることに最も心を砕かれたのです。こうした説法態様を「対機説法」といいます。
当時、お釈迦さまの教えに接した者の数は膨大であったはずです。当然その意味内容は多岐にわたったことでしょう。果たして、後世それらの教説を経典としてまとめてみると、相互に矛盾するようなことが少なくありませんでした。結果、どの教えがお釈迦さまの真意なのかが問題となり、学派が形成されるようになりました。
現在、日本には十三宗百派といわれるほど多くの宗派が存在します。こうした派生の源流も、究極的にはお釈迦さまの真意の探求という問題意識に遡ることができるといえます。したがって、いまの日本の現状は、お釈迦さまの自由自在な説法に由来しているといえるでしょう。
平成24年度 神奈川仏青 回答
Q お寺にはどうして梵鐘があるのですか?
梵鐘の「梵」はサンスクリット語の「神聖・清浄」を意味するBrahman(ブラフマン)の音訳であります。
本来梵鐘は、初期大乗仏教で教団生活を規制するために使われていたものであり、後に寺の存在を示し、大衆と仏教のつながりを保持するものとなりました。
現在の梵鐘の主な役割としては、法要など仏教における儀式の予鈴として撞かれる梵音具として重要な役割を果たしています。また、梵鐘は朝夕の時報として撞かれることもありますが、ただ単に時報として撞かれるものではなく、鐘の響きによってあたりの空気を清め、鐘の音の余韻のなかにお参りする気持ちを込めるものとして、その響きを聴く者は一切の苦から逃れ、悟りに至る功徳があるとされます。こうした梵鐘の功徳については多くの鐘の銘に記されています。
平成24年度 北総仏青 回答
Q 正座の歴史について教えてください
大変難しいご質問です。はっきりしたことが言えませんが、参考までにお答えいたします。
現在知られている正座、両足を折りたたみ、その両足首に腰をのせるというこの座り方は、実は呼び名がたくさんあって、しかもそれらを一まとめにして「正座」と呼ぶようになったのは最近のことらしいのです。それとは逆に、というのでしょうか、古い文書には正座の文字がでてくることはありますが、それは現在の正座ではなく、当時の正式な座り方を指しているようです。あぐら座りや片ひざを立てた座り方といった、現代では楽な座り方、あるいは状況によってはだらしないとみなされる座り方も、時代によってはそれが礼儀にかなう座り方だったわけです。
正座の起源についてはっきりしたことはわかりません。少なくともアジア地域では、このように足を折りたたんで座る姿勢そのものについては、古い時代から知られてはいたようです。しかし、今も昔も正座をすると足が痛くなるのは共通だったでしょうから、何らかの儀礼など特別な状況以外では、長時間正座をすることは少なかったと考えられます。
日本における正座の歴史もはっきりしていません。正座の姿勢をとっているような土偶や埴輪が出土していることから、この姿勢そのものは古代から存在していたと思われます。他方、古代の中国では正座が広まっていた時代があり、そこから日本に伝来したということも考えられます。どちらにしても正座は特殊な座り方で、通常はあぐら座りが普通でした。また、あぐら座りがだらしないという感覚はなく、身分の高い人間も格式のある場面においてもあぐら座りをしていたようで、むしろこちらの座り方が正式な座り方だったと言えます。
正座と宗教、特に仏教との関係を考えてみます。日本の仏教にはインド由来の伝統的な座り方として、結跏趺坐(けっかふざ)および半跏趺坐(はんかふざ)という座り方が伝わっています。両足首をそれぞれ反対の足のふとももにのせるのが結跏趺坐、どちらかの足を同様にのせるのが半跏趺坐です。これは密教修法や坐禅に用いられる座り方で、古くから変わらない姿勢で伝承されてきました。ですから僧侶が古代から結跏趺坐という座り方をしていたことは確かです。しかし正座については、今では僧侶は正座するものという印象が定着していますが、それがいつから、どのくらい正座が取り入れられるようになったかよくわかっていないのです。
古くから伝わる仏への礼拝法として五体投地礼というものがあります。立って合掌した状態からしゃがみこんでひざまずき、両手を前に突き出して上体を伏して頭を地面につけるというやり方です。この途中の姿勢というのでしょうか、ひざ立ちして合掌する長跪(ちょうき)というものもあります。これらのひざ立ちの姿勢から腰をおろすと正座の姿勢になりますので、現在正座と呼ばれる「姿勢」が長時間そのままでいる「座り方」として認知されていく過程に、仏教僧侶が何らかの形で関わったのかも知れません。日本の古代から中世にかけて、日常的な座り方として正座を用いていた可能性が最も高いのは僧侶たちである、とは言えると思います。
特殊な座り方であったと思われる正座が、日常の座り方として広まっていくのは江戸時代になってからです。戦国の世が遠いものとなってからは、武士階級のあいだでは儀礼や作法が重視されるようになりました。そのような風潮の中で、これまで一種特殊な、長時間座ると苦しい正座が、行儀の良い姿勢としてあえて作法に採り入れられるようになったようです。武士の正式な座り方として次第に定着し、次に町人達に広まっていったと考えられます。正座の姿勢と、「正座」という名称が一致して一般的に定着したのは昭和に入ってからのようです。
平成24年度 南総仏青 回答
Q 元三大師の御札のおまつり方法について教えてください
元三大師良源様は比叡山中興の祖である一方、全国から篤い信仰を寄せられる奇特のお大師様であります。
お大師様への信仰は史実とは別に、伝説や教化利益の物語が有名であります。中でも、異形の姿の角大師やコミカルな姿の魔滅(豆)大師、鬼の姿の降魔大師の御札はよく知られており、比叡山横川の元三大師堂だけでなく全国の寺院でも授与されております。
これらの御札は、それぞれ疫病神の流行を鎮めるためであったり、豊作の祈願に対して観音の三十三身に化身して田作りしたり、誘惑という大厄を祓ったりするために、お大師様が変化したお姿を写し取ったものなのです。
どの御札も災難や魔除けのためなので、家の中に魔が忍び込まないよう、神棚や仏壇、玄関の見返りや家の壁面の上方などの清浄な所に貼っていただけると良いと思います。
平成24年度 埼玉仏青 回答
Q お経の冒頭にある如是我聞ってどういう意味ですか?
如是我聞・・・我れ是の如く聞けり・・・ワレカクノゴトクキケリ・・・・? つまり「私はこういう風に聞きましたよ。」ということです!
お釈迦様のお弟子にアーナンダという方がいました。アーナンダさんはとても立派なお弟子さんで、いつでもお釈迦様のすぐそばにいて、たくさんのお説法を聞いていました。
さて、お釈迦様が入滅されてしばらくすると、残された人々はお釈迦様のありがたいお話をまとめていつまでも残していたいと思い、お釈迦様のお話を聞いて覚えている人たちを集めました。その集会に参加したみんなは、自分がお釈迦様から聞いたお話しを披露しました。
その中でもアーナンダさんは、一番たくさん説法を聞いていたので
「私はこのように聞きました、・・・・・・・・」
また、別のお話も、
「私はこのように聞きました、・・・・・・・・」
そのまた、別のお話も、
「私はこのように聞きました、・・・・・・・・」
そのまたまた、別のお話も
「私はこのように聞きました、・・・・・・・・」
・・・といったようにたくさんのお話をしました。
この時に、みんなで集まって話し合ったお釈迦様との思い出が、あとになって「お経」として文字にまとめられました。
だからお経は「如是我聞」で始まるのです。「如是我聞」とは、お釈迦様の本当のお説法ですよ!という証拠かもしれませんね。
平成24年度 群馬仏青 回答
Q お坊さんはどうして托鉢するのですか?
托鉢は托鉢行といい、沢山ある修行の一つです。主に食べ物を頂くための行ですが、いろいろな方から少しずつ頂きますので、自分の好きなものだけというわけにはいきません。時には嫌いなものがあるかもしれませんが、有難くいただくことで物に対する執着をできるだけ無くすために行います。
修行中のお坊さんは生活に必要なものしか持たず、又、修行に集中できるように作物を育てることはしません。しかし、お坊さんも食事を取らなければ生きていけませんので、一般の方から食べ物を分けていただかなければなりませんでした。そこで、托鉢を行うようになりました。
仏教を開いたお釈迦様も托鉢がとても大切な行だと考え、修行の基本としました。
ただ現在では、この托鉢精神を生かし、募金活動等を行っております。
平成24年度 茨城仏青 回答
Q 仏教と神道は両方おがんでよいのですか?
まず、仏教と神道について簡単に説明したいと思います。
仏教とは、紀元前五世紀頃(今からおよそ2500年程昔)に、インドでお釈迦様によって伝えられた教えです。
一方、神道は、太古の昔から日本において自然発生的に産まれた宗教で、山や川、水や火、草や木、こういった自然の万物には神が宿るとした、自然信仰や先祖崇拝などを大切にしてきた宗教です。
インドで生まれた仏教の教えは、東アジアを経てこの日本にも入ってくると、日本人はそれを受け入れ、次第に神道と仏教は融合していくようになり、そのような状態を、神仏習合や神仏混淆(こんこう)と呼んでいました。
ですから、僧侶が神社で拝んだり、寺院の入り口には鳥居があったり、神社の境内に仏塔があったりすることは、ごく当たり前のことでした。それが、明治政府により、神道と仏教が明確に分けられて、現在のようなかたちになりました。しかし、長い間、日本では神と仏は同じように奉られ、崇拝されてきました。
日本人が古来から大切にしてきた、先祖崇拝や自然信仰は、仏教や神道という枠にとらわれず崇拝されてきたものであり、我々はこれから先も、ずっとその事を大切にし、常に感謝する気持ちが大切だと思います。
平成24年度 栃木仏青 回答
Q 真言の読み方が、なぜ天台宗と真言宗で違うのですか
手に印を結び、口に真言を唱え、心に仏の姿を想う、真言密教は、天台宗(台密)と真言宗(東密)に伝えられています。この真言の読み方について、それぞれ読み方が異なっている場合があります。例えば不動明王の真言になると、
「天台宗」
ナマクサマンダバサラナン……
「真言宗」
ノウマクサマンダバサラダン……
と違いますし、光明真言になりますと、
「天台宗」
オン アボキャ ビロシャナ……
「真言宗」
オン アボキャ ベイロシャノウ……
と微妙に違いがあることがわかります。また流派などによっても読み方が異なります。
この違いは、天台宗では中天音(中インドの発音)、真言宗では南天音(南インドの発音)を用いるからです。なぜ違う発音を用いるのか、それは伝承によるものとしか言えません。ただ真言宗では、大日如来の宝塔(南天鐵塔)の伝承を大事にするので南天音を用い、天台宗では、当時のインド仏教の中心地である中天竺の発音を用いると見る事ができます。
平成24年度 福島仏青 回答
Q 写経がブームですが、やりかたを教えてください
コピー機で簡単に文章を複写することができ、さらには電子書籍のようにダウンロードという手軽さで何時でも何処でも書物を手に入れることができる現代ですが、写経が見直されています。写経に没頭できたこと、書き終えた達成感や開放感などを感じる方が多いようです。ただし、それには写経にふさわしい環境を整えることが重要です。特にこれから写経を始めようという方にとってはなおさらです。まず写経の間、他からの連絡などで邪魔されない静かな場所で行うのがよいでしょう。
次に写経作法についての一例です。
● まず手を洗い、口をそそいで、心身を清めます。
● お線香を一本立て、墨を仏さまにお供えした水ですります。
● 写経を始める前に合掌して、一度、浄書するお経を読誦します。
● 経文手本(台紙)に薄紙を重ねて、一文字一文字を急ぐことなく丁寧に書き写して行きます。
● 筆は毛筆が最適ですが、ペン・ボールペン・サインペン・鉛筆等で書写しても結構です。
● 「為」部分には写経した方のお願いごとをお書きください。例:家内安全、先祖代々菩提、学業成就、身体健康、心願成就など。
● 写経が終わりましたら、合掌し、一度浄書されたお経を読誦してご祈念ください。
書き上げたお経は、納経されることをお勧めいたします。近所のお寺もしくは菩提寺までご相談されるのがよいでしょう。天台宗としても推奨しておりますので、詳しくは天台宗公式ホームページをご覧ください。
写経によって心の眼を開くことを説かれた慈覚大師の浄行にならって『法華経』を写す「如法写経」は、連綿と比叡山に受け継がれて今日に至ります。また各地に写経会を行っている寺院がありますので、参加してみてはいかがでしょうか。
平成24年度 陸奥仏青 回答
Q 塗香について意味や作法を教えてください
塗香は、お香によって身体を浄めるために行います。お坊さんは法要に於いて壇に登り、まず最初に塗香の作法を行ない心身を浄めるのです。
天台宗の作法としては、まず右手の人差し指と中指で香をつまみ、最初に額、次に口で少し含むように、最後に胸の前で両手に広げ手を交差するように三度体に塗りつけるようにします。これで身口意(体・体内・心)を浄らかにしたという事になるのです。
塗香は漢方薬として日本に入ってきたという説があります。お坊さんは特別な法要の時に誓水(せいずい)という水を飲む事があるのですが、これに塗香を溶いて更に念を入れて体内を浄らかにする事もあります。
そもそも塗香に限らずお香(塗香・含香・抹香・線香など)とはその香りを仏様に捧げ浄めるために使われています。ですので、その時々において様々なお香が使われ、塗香はその中でも自身を浄めるために使われる最も基本的なものという事です。
平成24年度 山形仏青 回答
Q お坊さんで阿闍梨と呼ばれている方がいますが、阿闍梨とはどのような方ですか?
阿闍梨とは、密教の最も重要な儀式である伝法灌頂にて、師より法を授けられた僧侶の職位を指します。しかし、決して密教だけのものではありません。
この言葉の語源は梵語であり、弟子を教え、その行為を正しく導く師匠というような意味です。
仏教では、集団の中での立ち居振る舞いや衣食住の生活の規範となり、出家儀式などの中でその方法を教えた僧侶を阿闍梨というようになりました。
また、歴史的には平安時代に、皇族や貴族の子弟の中からその人に限り許された「一身阿闍梨」という称号や、比叡山や金峯山などの七つの霊山でのご祈祷の勅命を受けた「七高山阿闍梨」という称号もありました。特に京都の東寺の長者(貫主)は古来より「一ノ阿闍梨」と呼ばれてきました。
現代では、一般的に密教行者の僧侶の尊称として「阿闍梨」を使うことが多く、延暦寺の千日回峰行を満行なさった高僧に対して、親しみと尊敬の念を込めて「阿闍梨さん」とお呼びすることがあります。
平成25年度 京都仏青 回答
Q 檀家と信徒ってどう違うのですか?
檀家とは、梵語の「ダーナ」という言葉から生まれたもので、布施という意味です。「ダーナ」が「檀那」になり「檀家」と呼ばれるようになりました。
檀家は、あるお寺に所属し、その家の葬祭供養などをその寺に任せ、お金や衣食などの布施をし、それによってお寺を護持しています。また、檀家寺は過去帳により檀家の戸籍管理も行なっていたようです。
信者は、無病息災、良縁成就、五穀豊穣、商売繁盛といったことを仏・菩薩に願い、また、自身の心のよりどころとして、宗教、宗派、特定の仏さまなどを信じる個人です。
檀家寺でも、祈祷を行なったり、五穀豊穣を願う法要を行ないます。檀家であり信者でもある人を「檀信徒」と呼ぶこともあります。
平成25年度 近畿仏青 回答
Q 六地蔵さまにはどういう意味があるのですか?
お地蔵さまはお釈迦さまの入滅後、弥勒菩薩が出現されるまでの長い無仏時代に私たち衆生を六道の迷いの世界、即ち地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上界から救い、自らも仏になるために修行をされている菩薩さまです。特にお寺や墓地の入口に祀られている六地蔵さまは亡者が成仏出来ず、この六つの迷いの世界から抜け出せない状態、六道輪廻の世界に陥らないようにとの願いを込めて各地で祀られてきたものです。
私たち人間は、日頃、欲望を良心によってある程度コントロール出来る状態であるのに欲望の果てない自我が剥き出しになり、本能のまま動く智慧を失った世界や、常に争う、自我の心から生じるお互いの角づきあいの状態の世界に陥ってしまう危うい心を持ち合わせています。このような様々な煩悩に支配されないよう、迷いの心から抜け出すことをお釈迦さまは説き示されています。六地蔵さまが佇む姿から、日々の私たちの心の中の状態を見直すことが大切です。六地蔵さまは常に衆生の生死を超越して私たちのすぐ傍で救いの手を差し伸べておられるのです。
平成25年度 兵庫仏青 回答
Q ご本尊とはどんな仏さまですか?お寺によって違うのはどうしてですか?
あなたの知っている仏さまはどんなお名前の仏さまでしょうか?阿弥陀さま、或いはお不動さま、観音さま?又、その仏さまのことを「○○さん」と呼んだことがある方は多いのではないでしょうか。「阿弥陀さん」とか「お不動さん」「お薬師さん」といった具合です。「阿弥陀如来」というと堅苦しい感じですが、「阿弥陀さん」と呼ぶと何だか親しみが湧いて来ますね。ご本尊も「本尊さん」と呼ばれることが多いような気がします。
本尊さんはお寺によってゆかりのある仏さまをお祀りしています。その本尊さんを頼る理由は人それぞれです。例えば、亡くなった方のご冥福を祈る為に、阿弥陀さんをご本尊としてお参りしますし、病気の時には、病気平癒を祈願する為にお薬師さんにお参りをします。と言ったように、私達の悩み事や願い事は様々ですので、仏さんも色々なお姿になって顕れます。
仏さんは、山・川・草・木と至る所にいらっしゃるのですが、私達の煩悩が邪魔をして普段は目にすることが出来ないようです。だから煩悩のある人でも理解しやすいように色々なお姿でそれぞれのお寺に安置されています。だから本尊さんは一つに定まっていません。私達の悩みが沢山あるから一つに定まらないのですね。
自分の悩み事・願い事に合った本尊さんを求めて色々なお寺にお参りされてはいかがでしょうか。
平成25年度 岡山仏青 回答
Q 観音さまには色々なお名前がありますが、どんな種類の観音さまがいらっしゃるのでしょうか?
観音さまは、仏像や、仏画で様々な姿形に表されています。顔や手がたくさんあったり、すこし異様とも思える姿をした観音さまを変化観音といい、天台宗では主に六種類に分類されたものを六観音といいます。それぞれ、
正観音(もしくは聖観音) 〈インドの貴人の姿。変化する観音の最も基本となる。手に水瓶や蓮の花を持つ〉
千手観音(正式には十一面千手千眼) 〈お顔が十一面あり、加えて手が千本、目が千個(多くは省略される)。千は無限の救済力を表す〉
馬頭観音 〈六観音の中で唯一、怒ったお顔。多くは頭頂に馬の顔が表される。馬が草をむさぼるように、私たちの迷いや、煩悩を食べつくし、厳しいお顔で良い方向へと駆り立てて下さるという〉
十一面観音 〈十一のお顔を持つ。あらゆる方向を見渡し、世の中の救いを求める人を観察し、救う〉
不空羂索観音 〈お顔、手の数は様々。羂(網)と索(綱)を持ち、迷える人々を漏らさず救う(不空)〉
如意輪観音 〈六本の腕を持ち、片膝を立てて坐す。あらゆる願いをかなえる如意宝珠と障害を打破し、教えを広める車輪を象った輪宝をもつことから如意輪と呼ぶ〉
以上の六観音の他にも、国や時代によって沢山の姿形がありますが、これらは観音さまの信仰が古くから盛んであることを示すとともに、人々の求める理想像が反映されてきた証であるといえるでしょう。
平成25年度 四国仏青 回答
Q お線香は何本立てるのですか?焼香の作法さほうはどうするのですか?
~お線香とお焼香の心得を見つめよう~
皆さん日常生活のなかでお参りをされる際には、大体お線香をあげたりお焼香をされると思いますが、今日はそのお線香のお供えの心得をみつめましょう。
先ずお線香でございますが、三本立てていただくことをお勧めいたします。「三」という数は仏教において、三宝(仏・法・僧)、三世(過去世・現世・未来世)、三毒(貪・愼・痴)などに代表されるように関係の深い数でございます。自身の中の深い欲(貪)と苛々としてしまう気持ち(愼)や不平不満の言葉(痴)の三毒を焼き尽くし、三世に感謝し三宝を尊ぶ精神を養うこと、また火が一度着いたら最後まで燃え尽きるということから仏教でいう六波羅蜜の精進(たゆまぬ努力)を表すものでもございます。お線香の良い香りは仏さまやご先祖さまへあげられるお供物でもございます。最近では香りも少なく煙も出ないようなお線香もみかけたりしますね?もしもあなたが味のしない食事をだされたらどうでしょう?「あぁ、美味しいなぁ」と感じることが出来ますでしょうか?同じように仏さまとご先祖さまへお供えされるものもそうだと感じませんか?ならば、真心という感謝もこめて良い香りのお線香をお供えいただきたいと思います。
次にお焼香ですが、一回もしくは三回というのが主流のようです。
おそらくお葬式やご法事の際にされることがほとんどではないかと思いますが、その時に回数にこだわりを持つことよりも、大事なことはあなたがされるお焼香の煙がその部屋を満たすと同時に、故人やご先祖さまへご供養の気持ちを届けるんだ、さらには仏さまの世界に拡がっていくんだ、という気持ちでお焼香をしていただきたいと思います。
最後に、お線香やお焼香は仏事にこだわらずご家庭で日常焚いていただいてよいものでございます。古来より香のかおりは心の邪気を鎮める作用もあるようです。併せまして、大事なお客さまをご自宅へお迎えされる際など玄関で香炉に良い香りのお線香を焚くのもよき日本の「おもてなし」の作法(心)ではないでしょうか。
平成25年度 九州西仏青 回答
Q 授戒について。また、結縁潅頂とはなんですか?
~お授戒と結縁潅頂~
天台宗の宗祖伝教大師さまは、我々の誰もが仏さまの心になることのできる種(仏性)を生まれながらにして持っていることを自覚し、利他の行動をなす菩薩として生きて行くことが大切であると説かれ、我々が生きていく指針をお示し下さいました。
その指針の中心となるのが円頓戒であり、円頓戒を授かる儀式のことをお授戒、もしくは円頓授戒会というのです。
お授戒では、円頓戒の三つの大きな柱について、各自が誓いを立てます。一つには、自己の行いを慎み悪いことをしない(摂律儀戒)。二つには、善行を積み自己を高めることに努める(摂善法戒)。三つには、人々や社会のために尽くす(摂衆生戒)。これらは三聚浄戒といって、お互いに関連しあっており、我々すべてが自分の心の中におられる仏さまを自覚する源となるのです。
次に結縁潅頂ですが、こちらは密教の行事であります。「結縁」とは仏さまとご縁を結ぶこと。「潅頂」とは頭頂に水を潅いで仏法の正当な継承者となる儀式のことです。密教の儀式ですから、その内容について詳しく述べる訳にはいきませんが、仏法に沿った生き方をしていくことを心に刻む儀式だといえます。
お授戒も結縁潅頂も、実際に受ける際には僧侶より詳しい説明がございます。大切な儀式ではございますが、難しく考えすぎずに、私が生きているこの道は仏さまと繋がっているのだ、と実感できますよう、ご参加下さい。
平成25年度 滋賀仏青 回答
Q お供え物はなにをしたらいいのですか?お供えしてはいけないものはあるのですか?
何をお供えしたらいいのかということですが、何でもいいと思います。何でもいいというのは言葉が適切ではないかもしれませんが、特にこだわる必要はないという意味です。故人が好きだったものが良いかもしれません。果物も同様に何でも良いと思います。ただ日持ちがしないものが多いので1日ぐらい(何時間かだけでも)お供えした後はお下がりとして召し上がってください。お菓子やお饅頭の場合も同じです。腐るまでお供えしておくのでなく食べられるうちに下げて召し上がるのが良いと思います。何日間とかではなく毎日お供えしてください。お菓子や果物は毎日交換する必要はないと思いますが(果物は供えられていない日があっても良いと思います)タバコやお酒も故人が好きだったのならお供えしてあげてください。缶に入ったものは開けても開けなくてもいいように思います。
最後になりましたが大切なのは気持ちだと思います。いくら良いもの、高いものをお供えしていても「してあげている」というような気持ちならばしないほうがいいです。安いもの、賞味期限が切れかけのものをお供えしていても「させていただく」という気持ちであれば故人も喜ばれると思います。またお供えしているからといって放っておいては意味がありません。仏壇の前に座って手を合わせることは大切なことだと思います。
平成25年度 山陰仏青 回答
Q 袈裟とはどのようなものですか?
袈裟とは、私達仏教の僧侶が身に着ける法衣(衣装)の名称で、元々は古来インドでごみために捨てられた糞を拭ったようなぼろ布をつなぎ合わせて作ったところから糞掃衣とも呼ばれました。現在日常で使われている袈裟のほとんどは新品の布で作られますが、古来の名残りから、小さくした布を継ぎ合わせて作られているのが特徴です。
袈裟といっても、五条袈裟、地蔵袈裟、如法衣等、さまざまな種類があり、一般の方には、葬儀の際、お導師の方が着けられる豪華絢爛な七条袈裟が一番イメージしやすいかと思います。
また檀信徒のかたが、お参りの際、首から下げて用いる半袈裟も立派な袈裟の一つです。天台宗では半袈裟は檀信徒向けで、輪袈裟は僧侶が使うものです。その輪袈裟も実は古い歴史があります。平安時代に天台宗の高僧・慈覚大師円仁が唐(中国)へ留学中、仏教の弾圧騒動が激しく身に危険がおよんだ際、円仁は袈裟を折りたたんで首にかけることにより、なんとかその難を逃れたという有名なエピソードがあり、天台宗の僧侶が常用する輪袈裟の起源となっております。このように身近な物からも長年の歴史、そして先徳をうかがい知ることができ、とても興味深いですね。
平成25年度 三岐仏青 回答
Q 得度とは、どういう事をするのですか?
得度とは、将来僧侶になるための第一段階、つまり僧侶になるための入門式のことです。得度の「度」は「度牒」と呼ばれ、見習い僧侶(小僧)になった証明書のことをいいます。得度式では、頭髪を剃り、延暦寺戒壇院の裏側にある蔵髪堂にその髪を納めます。たとえ10歳の子供であっても、剃髪をすることでこれから僧侶になるという覚悟を持つことになるでしょう。
このような得度式を済ませると、小僧として日々師匠に仕えて、掃除をしたり、お給仕をしたりといった生活をしながら、お経の読み方や内容など様々なことを学びます。こうして仏道修行に専念する人のことを出家といいます。一方、日々の生活を営みつつ出家者に布施をし、簡略な戒律を守って修行する人のことを在家と呼んで区別しています。
得度の後、数年間の修行生活を経て、戒律を授かり、正式な僧侶(大僧)となるのです。
平成25年度 東海仏青 回答
Q 数珠の意味はなんですか?
数珠には、色々な大きさのものがあり、宗派によって異なりますが基本形というのはきちんとあります。珠の中で一番大きいもの母珠または親珠と言い、ご本尊を表しています。親珠の左右には同じ大きさの珠が全部で108個あり、煩悩の数を表しています。煩悩は私達の持つ様々な欲望のなせるものであります。人間は動物の一種でありますから、基本的には欲望に基づいて思考し、行動することによって生命を維持しています。人間は「これでよい」という限度を越えて欲望を追い求めがちであります。数珠を身につけることはその欲望・煩悩をコントロールするという誓いの証でもあります。私達は、何時も懺悔とお誓いの気持ちを忘れず数珠を大切にしましょう。
平成25年度 北陸仏青 回答
Q 戒名にはどのような意味があるのでしょうか?
本義としての戒名とは、戒を受けた者に授ける仏弟子としての名前のことです。戒とは仏弟子として守るべき事柄のことです。特に天台宗での戒は十重四十八軽戒を指します。
今日において、戒名とは死を仏さまとの縁として仏法に帰依した者に授ける名前のことをいいます。葬儀式の中には戒を授ける作法が組み込まれており、そのため、葬儀式を終えた後に正式に戒名を授かることになります。
戒名を授かることができるのは、死後に限ったことではありません。先に本義として述べたように、戒名とは戒を授かり仏弟子となった者に与えられる名前です。檀信徒の方で生前に戒名をお受けになりたいと願う方は、授戒会などで戒を受け、戒名を授かることができます。
どのような戒名が良いかについては、明確な基準はありません。ただし、戒名中に故人の生前の人柄、徳、性格、職業、趣味など生前の行状と深いつながりのある語句が使用されていると、いつでも故人を思い出し偲ぶことができると思われます。
戒名は、俗名と違ってどうしてもなじみの薄いものです。しかし、仏弟子としてこの世から浄土へと生まれ変わった後のお名前となるものです。故人の思い出と共に大切にしたいものです。
平成25年度 信越仏青 回答
Q 六波羅蜜とはなんですか?
「私たちの生活している迷いの世界と、仏の悟りの世界の間には、煩悩の渦巻く大きな川が流れている」、という有名な喩えがあります。
六波羅蜜とは、この喩えにある大きな川を渡りきる為の修行法を六つにあらわしたもののことです。悟りへ到達する為の実践行ですが、言い換えるならば、私たちが人生をより良く生きていく為の六つの実践法とも言えます。
その六つの方法とは、布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧というものです。
・第一の布施とは、品物や金銭を施すなど、見返りを求めず、他人にそっと手をさしのべること。
・第二の持戒とは、規則正しい生活をすること。
・第三の忍辱とは、怒りの感情をおさえて、自ら反省し耐え忍ぶこと。
・第四の精進とは、何事をするにも努力をおしまないこと。
・第五の禅定とは、自分が今なしている事に心を集中すること。
・第六の智慧とは、物事の正しい判断をすること。真理を見極める心。
普段からこの六つの方法を実践し、努力することはなかなか大変なことですが、希望と反省は忘れず、少しでもこれらの心を育めるように日々を過ごしたいものです。
平成25年度 神奈川仏青 回答
Q 千日回峰行とはどんなことをするのでしょうか?
千日回峰行は比叡山に伝わる修行の一つで、相応和尚(831~918)を創始者とします。行者は、比叡山の霊跡を巡礼する回峰行を行います。回峰行をおよそ7年かけて千日間行うことから千日回峰行といいます。
行者は、浄衣という白装束、草鞋履で比叡山の峰々を巡ります。行者の出で立ちが不動明王を模しているのは、回峰行を行うことにより、身も心も不動明王と一体となり人々を救うことを目指しているからです。
比叡山の教えの基本となる『法華経』には、全てのものは仏になる素質を持ち、全てのものは仏となることができる。故にあらゆるものを軽んずることなく尊び大切にするという教えが説かれています。また比叡山には、「草木国土。悉皆成仏」という、世界を構成するすべてのものが仏様になることができる、との教えもあります。故に行者は、お堂にお祀りされている仏様のみならず、ありとあらゆるものを仏様とみなして、比叡山を回るのです。
七百日目の回峰を終えると「堂入り」と呼ばれる行に入ります。その間、行者は断食・断水・不眠・不臥(横にならない)で9日間、一心に不動明王を念じ続けます。「堂入り」を遂げると行者は生身の不動明王とされます。「堂入り」を遂げるまでの行は、主に自身のためのものですが、以後の行は、主とするところが衆生救済のために変わり、人々の規範となり多くの人を導く立場に立つことから、人々は親しみをこめて「阿闍梨さん」と呼んでいます。
「堂入り」の翌年、行を始めて6年目には、基本の行程に赤山禅院への巡礼が加わる「赤山苦行」(行程約60㎞)が行なわれます。
また満行となる7年目には京都市中に入り、親しく市中の人々のために祈り巡礼する行程約80kmにも及ぶ「京都大廻り」を行います。その後、行者は基本の行程30㎞の回峰を七十五日間行い、七年間で975日の回峰を以て一千日の修行を満じ「大行満」となります。行者が7年間の回峰行中に歩く距離は、地球一周分の約40000kmにも及びます。
大行満となった行者は、後に京都御所において、土足で参内し「玉体加持」を行う「土足参内」が許され、これを勤めます。なお、回峰を975日間で終えるのは、行者の修行に終わりはなく、修行は一生続いているということをあらわしているとされています。
平成25年度 本山仏青 回答
Q 天台教学の「一切衆生悉有仏性」とはなんですか?
「一切衆生悉有仏性」とは、『涅槃経』というお経に出てくる文言です。現代語にすると「生きとし生けるものはすべて生まれながらにして仏になる素質をもっていますよ」という意味です。
この「仏になる素質」というものを、お寺の幼稚園などでは以下のように園児さんに伝えることがあります。
「みんなの心の中には、『ほとけさまの種』が入っています。それを大切に育てましょう。」
ここで言う「ほとけさまの種」こそ「仏になる素質」のことです。「ほとけさまの種」は「ほとけさまのお花」を咲かせます。仏教で花といえば、蓮の花を思い浮かべる方も多いでしょう。蓮の花は濁った泥水の中から芽を出し、きれいな花を咲かせます。私たちも生きていく中で、色々なねたみ、不満、愚痴など濁った泥水のような心をもってしまいます。しかし、種に栄養を与えるときれいな花が咲くように、それらの気持ちを振り返り、解決や反省をすることで、ほとけさまのような清らかな心に近づいていくのだと思います。
「『ほとけさまの種』は誰でも持っており、花を咲かせる努力はいつでも誰でもできますよ」ということが、「一切衆生悉有仏性」という言葉の真意なのではないでしょうか。
仏教にはたくさんのお経・教えがありますが、天台宗ではそれらは別々な悟りに至るための教えなのではなく、全てはお釈迦さまと同じ悟りに至るための教えであり、大切なものと考えます。
平成25年度 東京仏青 回答
Q 四十九日とはどういう意味ですか?
最近の葬儀では、葬儀式に引き続いて初七日法要を行うことが多いと思いますが、もともとは亡くなった日から数えて、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日(※読み方などは地域によって様々)と七日目ごとに法要を行っていました。その最後の日が四十九日です。七回目ですから、七回目×七日=四十九日で七七日というわけです。最後ですから尽七日ともいいます。
その四十九日までの期間を中陰といいます。四十九日の七七日忌法要を営みますと、これで中陰が明けることになります。四十九日のことを満中陰というのはこのためです。
また、中陰というのは中有ともいいます。中有というのは、この世と次の世との間にある世界といえましょう。すなわちこの期間は、故人が仏に成るためのとても大事な修養期間なのです。
葬儀式では僧侶が引導を渡しますが、これだけで故人が完全に成仏できたというわけではないのです。いうなれば、就職活動を終えて入社したばかりの新入社員が、まだまだ一人前とはいえないのと同じようなものです。
ですから、中陰期間中は喪に服し、故人の大事な修養期間を大切にし、日常生活を十分に謹んで、ひたすらに故人の冥福を祈るのです。そして四十九日には、故人の近しい方々に集まっていただき、お供物等を整え、法要をして故人の旅立ちをお見送りしましょう。
平成25年度 北総仏青 回答
Q 卒塔婆の意味はなにですか?何が書かれているのですか?
昔のインドで、亡くなられたお釈迦さまの為に、ストゥーパと言う供養塔が建てられました。『卒塔婆』はこのストゥーパの音を漢字に写して作られた言葉です。つまり『卒塔婆』とは仏さまを供養する為の塔を意味しています。
今では、皆さんが法事などで建てる板のお塔婆がこの『卒塔婆』になります。
また、『卒塔婆』には一番上に梵字と呼ばれる文字が書いてありますが、昔のインドでは大きなもので言えば地球や宇宙、身近なもので言えば私達人間など、全ての物は空・風・火・水・地の五つの要素から出来ているという考え方がありました。その大切な五つの要素を『卒塔婆』の上から梵字で記してあります。そしてその下に経文を書き、故人が仏さまのお弟子となった証しである戒名と年回忌を書いて故人そのものの供養塔になります。裏には大日如来の梵字が書いてあり、その下に建てた方のお名前と、その日付が記されています。
また、この『卒塔婆』は、前に書きましたが仏さまの供養塔(ストゥーパ)を表しています。日本では三重塔や五重塔がこれにあたりますが、皆さんが法事などで建てているお塔婆は三重塔や五重塔を建てるのと同じ功徳があるのです。そう考えるとお塔婆を建てる事の有難さがわかってくるのではないでしょうか。
平成25年度 埼玉仏青 回答
Q 仏前結婚式はどんな内容でおこなっていますか?
お寺で行う仏事と言えば、葬儀や法事といった印象から、仏前での結婚式って何?と思われていることだと思います。
そこで、仏前結婚式の流れとその意味についてお話します。
① 入 堂:新郎新婦・戒師(導師)が式場に入る
② 三 礼:仏・法・僧の三宝へ礼拝
③ 勧 請:諸仏・諸菩薩を式場に迎える文を唱えます
④ 表 白:諸仏・諸菩薩・ご先祖に結婚式が行われることを報告し、新郎新婦へのご加護をお願いします
⑤ 授懺悔文:三毒(貪【むさぼり】・ 瞋【いかり】・癡【おろかさ】)を犯さないことを誓います
⑥ 授三帰:仏・法・僧の三宝を信じて、疑わずに守ることを誓います
⑦ 法水頂戴:法水という、清めたお酒で三三九度の盃を交わし、新郎新婦のふたりはもとより、両家の固めの盃をいただきます
⑧ 念珠授与:仏教徒となった証に仏さまより念珠を授かります
⑨ 指輪授与:指輪の交換を行います
⑩ 聖句授与:戒師より仏さまのお言葉の中から人生の規範とすべき「聖句」を授かります
⑪ 証明授与:戒師より結婚の儀式が正しく執り行われたことの証を授かります
⑫ 宣 誓:新郎新婦が仏さま並びに参列者への誓いの言葉を読み仏前へ捧げます
⑬ 新郎新婦の献香:新郎新婦は香を捧げ、仏さまをはじめ一切に供養します
⑭ 法楽・回向:結婚式のお礼に仏さまやご先祖さまにお経を捧げます
⑮ 退 堂
以上が主な内容となりますが、地域や環境などによってやり方は異なります。また、宗派によっては全く異なることもありますので、あくまで1例としてお考え下さい。
仏前結婚式とは、二人が出会い結婚に至ることは、偶然ではなくお互いに深いご縁(因縁)によるものであり、このご縁を仏さまや親や親族、ご先祖へ感謝の報告をする場になります。
平成25年度 群馬仏青 回答
Q 坐禅のやり方を教えて下さい!
坐禅の中では「身・息・心」を整えることが大事です。
○「身」とは、坐禅を行う前の準備運動から、正しい坐禅の姿勢を整えます。
座布団の上にあぐらをかいて座る。(足の悪い方は椅子でも可)
① 首の運動として、前後、左右に動かす(各三回)
② 肩の上下運動。両腕を両側に垂らして、上下に動かす(三回)
③ 腰の運動。先ず左手を自分の後方に置いて、右手は左足の膝へ置いてから、腰を左向きにひねる。しばらくしてから手を置き換えて、右側に腰をひねる(三回)
④ 座布団の方は、座布団を半分に折って座る。足を組める方は左足を右足の股の上に載せる。
⑤ 背筋を伸ばして、胸の前で右掌に左掌を載せて親指の先をつけて楕円の輪を作り、そのまま下に降ろす。
⑥ 顎を引いて、目は半分瞼を閉じて目線は鼻先1メートル前方を見て動かさない。
○次に「息」とは呼吸の事ですが、鼻から吸って口からはく。途切れず、静かでスムーズな呼吸がベストですが、鼻が詰まる方や気分が悪くなる方は自分に合った呼吸をしてください。
○最後に「心」ですが、坐禅に慣れていない方は「数息観(すそくかん)」と言って、坐禅中は常にご自分の呼吸を数えてください。(吐いて吸って一つ、吐いて吸って二つ・・・と)百まで数えたらまた一つ目から数えて繰り返します。坐禅の時間は三十分間ぐらいから始めるのが良いかと思います。
○坐禅を終えるときには、最初と同じく整理運動を行って、全身をよくほぐしてください。
平成25年度 栃木仏青 回答
Q 先祖供養の仏さまはなんですか? やりかたはどうすればいいのでしょうか?
「本尊」
天台宗のお寺のご本尊は、阿弥陀如来さま・観世音菩薩さま・不動明王さまなど様々な仏さまをおまつりしています。
それらは法華経では釈迦如来と同一体とされ、すべて御縁に従ってこれらの仏・菩薩を敬信します。
寺院によってご本尊も異なりますので、それぞれの菩提寺のご本尊を先祖供養の仏さまと定めるのも一つの形ですが、阿弥陀如来さまをお仏壇にお祀りするのが一般的です。
「日常の先祖供養の方法は?」
お仏壇にお花・お茶・ご飯のお供えしてください。
お仏壇のない家庭では、タンスや小さいテーブルなどの上にご本尊(菩提寺のご本尊もしくは阿弥陀如来坐像)とお位牌をお祀りします。
蝋燭・お線香・お茶・ご飯・果物や生前の好物をお供えしましょう。お供えしたら、お線香を焚いて手を合わせてください。
一日無事に過ごせたことなど、感謝の心をお伝えすれば、ご先祖さまは、その人や家族を守ってくださいます。
平成25年度 福島仏青 回答
Q お寺の法要でまく紙の花(散華)はどんな意味があるのですか?
花びらをかたどった紙を散華(さんげ)といいます。仏教では花の上というのは、清らかな場所とされています。お寺の仏像を見ると台座の部分に蓮の花などが彫ってあるものが多く見られますが、これは花の上という清らかな場所に仏さまがおられることを示しています。こういったことから、法要をする際にお堂の中を清めるという意味合いで花を撒いています。また、仏さまがおいでになられた際に花を散らして供養した故事にもちなんでいると言われています。
本来であれば本物の花を撒かなくてはいけないでしょうが、法要の度に沢山の花を用意するのが難しかった為に花を象った紙を撒くようになったのだと思われます。
他にも、仏さまが説法をされた際に天人が仏さまを讃えるために天より華の雨を降らしたとの伝えに倣い、法要の際に仏さまを讃えるために撒かれるようになったとも言われております。法要で散華を撒いた際には仏さまが花の上を歩いたということで、功徳があるお守りとして散華を持ちかえる人も多くいらっしゃいます。
平成25年度 陸奥仏青 回答
Q 大乗仏教とはどんな教えですか?
一言で言えば全ての者が仏になるための教えです。
仏教はお釈迦さまの教えから成り立っているわけですが、約2500年前にお釈迦さまが亡くなられた後に弟子たちによる結集が開かれ、お釈迦さまの教えを文字にし、これが経典となりました。その後に考え方の違いからそれぞれ流派(部派仏教)に分かれ、出家者中心で修行したものだけが悟りを得られるというものになりました。これがいわゆる上座部仏教です。そしてお釈迦さまの教えは全ての者を救うためのものであるという考えで、解りやすく編纂したのが「大乗経典」です。これを基にした教えが大乗仏教です。
主に大乗仏教は日本や中国、朝鮮半島などに伝わりました。ちなみにチベット仏教も大乗仏教だそうです。そして上座部仏教はタイやミャンマーなどの東南アジアを中心に伝えられました。
平成25年度 山形仏青 回答
Q 衣にはどんな種類があるのですか?色の意味はなんですか?
皆さんが良く目にするお坊さんの格好というのは、黒い衣に首から輪になった袈裟(けさ)を掛けている姿でしょうか。
これは直綴(じきとつ)という衣の袖を短くするなどして略された衣で、道服(どうぶく)と呼ばれる日常に着られる一般的な衣です。
僧侶が身につける衣には大きく分けると、腰につける袴(はかま)、全身を覆う法衣(ほうえ)、肩から掛ける袈裟(けさ)の三種類あります。
それぞれ法要や用途によって数種類ずつの形があり、合わせると二十種類ほどになります。
元来、仏教発祥のインドに於いては比丘(びく・僧侶)は三枚、比丘尼(びくに・尼僧)は五枚の衣の所有しか認められませんでしたが、
インドから中国に仏教が伝わった時、寒冷だった為に袈裟の下に法衣が着られるようになったようです。
初めはなるべく質素なものをということで、泥染めの衣を着ていたようですが、
それが手近にあって染めやすい材料として墨を使うようになったといわれています。
このように、インドから中国を経て日本へ伝来する中でそれぞれの国の気候や習慣に合わせて衣も変化してきました。
法衣にもいろいろな形がありますが、さらに僧侶の功績などによって決められた「僧階(そうかい)」ごとに定められた色があります。(緋衣、紫衣、松襲衣、萌黄玉虫衣、木欄色衣、黒衣など)
これはもともと中国の唐の時代の朝廷に用いられた礼服等に由来するものです。
平成25年度 北海道仏青 回答
Q 相応和尚について教えて下さい
延暦寺の第3世天台座主慈覚大師円仁の弟子です。比叡山に伝わる千日回峰行という修行をはじめました。 千日回峰行とは比叡山の山中を巡りながら、仏をはじめ、神、山、石など全てのもの仏様同様に敬い、祈り を捧げる修行です。相応和尚は「世の中のあらゆるものは仏になる素質がある」という法華経の教えの体現 者といえます。 また日本天台宗祖最澄と師匠の円仁への大師号授与を清和天皇に奏上しました。この実現によって日本で最 初の大師号となる伝教大師と慈覚大師が誕生したのです。
平成27年度 本山仏青 回答
Q 墓地を移転しようと思いますが、どんなことに気をつけたらよいでしょうか?宗教的なこと手続き的なこ とを教えて下さい
現在のお墓が寺院墓地にある場合、まずはその寺院の御住職にご相談されるのが良いでしょう。
法律にのっとった基本的な手続きは以下のとおりです。
1.移転先の墓地から「墓地使用許可証」を発行してもらう
2.現在の墓地がある市区町村から「改葬許可申請書」を取り寄せ、現在の墓の管理者から署名・捺印をもらう
3.1と2の書類を現在の墓がある市区町村に提出し、「改葬許可証明書」をもらう
4.現在の墓から遺骨を取り出す(この時、閉眼供養を行います)
5.石材店などに依頼し古い墓を解体、整地して管理者に返す
6.移転先の管理者に「改葬許可証」を提出する
7.遺骨を埋葬する(この際、開眼供養を行います)
なお、地域・自治体により必要な書類や手順が異なる場合もあるため、改葬を決められたら現在の墓地があ る自治体にまずは確認されるのが良いでしょう。 また、墓地には、運営管理者によって寺院墓地・公営墓地・民営墓地、等に分かれます。寺院墓地の場合、 「改葬許可申請書」の署名・捺印は運営管理者である寺院からもらうことになります。
平成27年度 京都仏青 回答
Q 「四門出遊」の意味するところを教えてください
お釈迦様が出家される前、釈迦族の太子の頃、カピラ城の東西南北の四門から城外に出られ、様々な人々・ 場面に遭遇し、出家を決意したという説話です。 太子は、東門で見るに堪えない老人の姿を見て、逃れられない老いの苦しみに直面し、南門では病に侵され た者に会い病の苦しみを知り、さらに西門では人の死に遭遇し、生きていればこの「老・病・死」の三苦が 避けられないものであることを知ります。 しかし北門ではそれらの苦しみを乗り越えんとする出家修行者、沙門と出会い、その煩悩を捨て去った崇高 な姿に心打たれて、自らも出家を決意されました。
平成27年度 近畿仏青 回答
Q お寺には住職がいますが、住職以外の身分、肩書きはあるのでしょうか?
住職以外に、住職を補佐する立場の副住職、主にご住職の奥方がなる寺庭夫人、または他に事務をされる方 がいる場合には執事長、寺務員等の様々な方々がいらっしゃいます。 天台宗では、基本的に寺院を取り仕切る者は「住職」とお呼びすればよいのですが、地域によって「お じゅっさん」や「法印さん」など様々な呼び方をされます。 また、門跡寺や大きなお寺では「門主(もんす)」や「貫主(かんす)」、「貫首(かんしゅ)」、「管長(かん ちょう)」など住職の呼称を決めている寺院もあります。 お呼びするときにはそれぞれ頭に「ご」をつけていただいて、「ご住職」や「ご門主」などとお呼びいただ くと丁寧でよろしいかと思います。
平成27年度 兵庫仏青 回答
Q 不動真言の意味を教えてください
不動真言とは、不動明王のご真言のことです。不動明王は仏道修行者を守る役割があり、修行者に寄り添って悟りを求めて修行する心(菩提心)を発し、悪を断じて善を行い、計り知れない智慧を得て、成仏さ せるということを目的としている明王(仏)です。 次に真言とは、仏教がインドで生まれた頃そのままの発音で、仏さまのお名前をお呼びし讃嘆する言葉と 言い換えることができます。仏や菩薩の本誓、迷いや苦しみなどから衆生を救うという誓いを示す秘密の言 葉です。不動真言は「ナマサマンダ・バサラナン・センダ・マカロシャナ・ソワタヤ・ウンタラタ・カンマン」(天台宗「台宗課誦」より)、概ね「遍く諸々の金剛部に帰依し、特に不動尊を呼んで煩悩・業障を破 壊し、大空の三昧に入ろうと願う」と訳すことができます。 千日回峰行を行う阿闍梨様が不動真言をお唱えするのも、修行中に出てくる様々な煩悩を菩提心にする為 にお唱えしています。阿闍梨様が生身の不動と呼ばれるのも弛まぬ菩提心を持っているからといえるでしょ う。堂入りなどの苦行におけるその精神力の強さに、私たちは自分の心の可能性に気付くことができます。
お不動さまは怖い顔で私たちを睨みつけ、邪心や気付かない内に持ってしまった煩悩を戒めて下さいま す。改まる時にはきちんと氏名を呼ぶように、正式なお名前で一心に真言をお唱えすれば、迷った心を正し い道に導いて下さることでしょう。
平成27年度 岡山仏青 回答
Q 声明とはなんですか?
古代インドのバラモン教の僧侶は「リヴ(讃歌)・ヴェーダ(智慧)」を唱えるとき、節付けをして歌うよ うに唱えていました。これを梵唄(ぼんばい)といいます。やがて梵唄は仏教に取り入れられ、中国へ渡り ました。中国で密教が盛んになると密教儀式の音楽として整えられ、7~8世紀渡来僧や留学僧によって我 が国にもたらされました。 承和14(847)年留学を終えて帰国された慈覚大師円仁は「曼荼羅供養会」「引声(いんぜい)阿弥陀 経」などの新しい梵唄をもたらしました。これが天台梵唄です。梵唄は時代を経るに従って唱える僧侶によ り幾らかづつ節回しが違ってきたり、また名称も声明に変わってきました。そのため室町時代のころ「声明 譜」が作られ、節回しの統一化が図られました。 声明の内容についてですが、如来や菩薩、経典、高僧を讃えた文句や、民衆に地獄や浄土がどのようなとこ ろかを覚えやすく説明するための文句に旋律をつけ、各時代に沿った声明曲が作られました。儀式の中では、 これに鐃・鉢(シンバルやドラのようなもの)を鳴らしたり、時には雅楽を付けたりします。また、慶事や 弔事、ご祈祷などではすべて異なる声明をお唱えします。機会がございましたらぜひ耳を傾けていただけれ ばと思います。
平成27年度 山陰仏青 回答
Q 天台宗の修行とはどのようなものであり、なにをするのですか?
修行は自ら行うものであり、誰かに無理矢理やらされるものではありません。
修業とは、仏の悟り(境地)を得ることを目的として行われるものであり、座禅・写経・托鉢から山に籠る 籠山・山を巡る回峰行などいろいろあります。 天台宗は伝教大師により円密禅戒すべてを学ぶ宗派として拓かれたので、経典(円)を学び、密教(密)を 修し、坐禅(禅)に勤め、戒律(戒)を守るということを主に修行します。また、これらは大乗仏教では自 分のために修行することを自行と呼び、自行によって得た心で今度は他の人たちを助ける利他行を行います。
平成27年度 四国仏青 回答
Q 修行の一つに四度(しど)加行(けぎょう)があると聞きました。どんなことをするのですか?
四度加行とは天台宗の僧侶となる上で必須の密教修行です。 天台宗の僧侶となるには、まず師僧様に弟子にして頂き、得度式という儀式を受けなければなりません。得 度式は、仏さまの弟子として精進していくことを誓う大切な儀式です。 得度式を終えると、いよいよ、比叡山行院という修行道場にて、60日間の修行を受けます。
まず前半は、天台僧としての基礎的な教義や儀式作法を習得する前行(ぜんぎょう)を行い、後半に四度加 行という密教修行を中心とした行を履修します。 この四度加行の中で、諸仏のご真言を何千遍も唱え、印の結び方の伝法を受けます。
四度加行は、十八道、金剛界、胎蔵界、護摩、の四種類で構成されております。 十八道は仏様を迎える18の作法です。 金剛界と胎蔵界は、それぞれ金剛頂経・大日経というお経に基づいての実習です。 護摩は四度加行の最終段階、仕上げの行となります。
この四度加行は、午前2時には起床し、冷水を浴び身を清め、一日三座の密教作法を行い、仏様をご供養す る厳しい行でありますが、この行を修めることで、正式な天台僧として認められるのです。
平成27年度 九州東仏青 回答
Q 位牌が多くなり整理したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
長い年月が経てばお位牌も古くなったり多くなってきたりしますが、いくら古くて多くなったからといって、 永年家族の人々が手を合わせ拝んできたものを簡単に捨てるということはできません。亡くなられた方の戒 名あるいは法号を記したお位牌は、亡くなられた方の「依代」として、またご先祖様や故人の象徴として拝 むわけですが、私たちが今ここにいるのはご先祖様のおかげでありますので、ご先祖様に対する感謝の心を 忘れないようにしていただきたいと思います。
まず菩提寺のご住職にご相談されるとよいのですが、遠くに離れていたりしてすぐにできないときは、近く のお寺に行って、古くなったお位牌の「魂抜き」のご供養をしていただき、「お焚き上げ」をお願いしたら よいと思います。お位牌を新しくされたときは、必ずご住職に「開眼供養」(魂入れ)をしていただいてから、ご安置ください。
平成27年度 九州西仏青 回答
Q 比叡山の紋に菊と法輪のようなものがありましたが、この紋は何ですか?
菊輪宝の事ですね。この紋は延暦寺の寺紋になります。延暦寺一山の僧侶が身につけるものです。 この菊は十六菊になります、皇室の紋章と一緒です。
天皇家でこの菊の紋が使用されているのは、伝教大師が桓武天皇に比叡山で採取した十六弁の菊の花を献上 した事が始まりと言われ、その為、天台宗では菊の紋の使用を許されていると云われています。また天台宗 は、京都の皇室を護るための宗派として始まったからです。京都御所の鬼門に当たるところから朝廷の安寧 と五穀豊穣を祈る鎮護国家の道場となり、勅許をいただいて延暦寺を建立して本山としています。
法輪とは、古代インドで使われた武器で輪の周りに刃物が付いています。 これは、釈尊の教えが悪を砕くという意味があり、輪というのは車輪の如く この釈尊の教えが車輪が回転するかのように転がって広く伝わっていく事の意を表しています。菊輪宝は本 山の比叡山延暦寺の教え、天台宗の教えが、広がっていく事を表した紋になります。
平成27年度 三岐仏青 回答
Q 如来や菩薩、天などと仏様によって違うのはなぜですか?(例、阿弥陀、地蔵、大黒)
先ず最初に... 仏様の世界は、如来・菩薩・明王・天部から成っています。
~如来~ 如来とは、悟った人、真理に到達した人、覚者という意味で仏の中の仏であると言えます。 そして、この如来のモデルは言わずと知れたインドの釈迦族のゴータマ・シッダールダ太子です。 シッダールダ太子は王宮を出る時に、豪華な衣装やアクセサリーなどは全て取って王宮を出た為、 身にまとっているのは一枚の納衣のみで武器や鎧も持っていません。 インド式に一枚の布を巻きつけた納衣と、素足で苦行をされたしるしの裸足こそが如来の特徴で あり、仏教で最初に誕生した仏様が如来です。 如来の主だった仏様には、この釈迦如来で、続いて阿弥陀如来、薬師如来、大日如来などがおら れます。
~菩薩~菩薩とは菩提薩埵を縮めた言葉で、悟りを求める人という意味です。 悟りの最高位に達した存在が如来で、菩薩は今まさに如来になろうと修行を重ねている存在であ ります。 菩薩はシッダールダ太子の出家以前の姿が基本となっているので、如来とは違い、頭に王冠をのせ て首飾りや耳飾りや腕輪といったアクセサリーを身に付け、きらびやかで装飾性が強い仏様です。 菩薩にも聖観音菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩をはじめ、この他にもたくさんの菩薩がおられます。
如来も菩薩も、主に慈悲深く衆生救済の誓願を持つ仏様方です。
~明王~ 明王は、如来がつくる浄土や法に危害を加える邪神や仏敵がいれば、激しく威嚇ししたがわない ならば、仏法護持のため武力をもって懲らしめる事が主たる役目です。 その為、燃えさかる火炎を背にとても恐ろしい形相で眼をらんらんとさせて睨みつけ手には宝剣 や羂索等の武器を持っているのが明王の特徴です。 よく知られている明王には不動明王、それに降三世明王、軍茶利明王、大威徳明王、金剛夜叉明 王などがよく知られています。
~天~ 天部の仏様は、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の六道の最上界の天に住む仏様で仏教を守り、 人々に幸福をもたらす仏様です。
東西南北を守護する四天王 東方の持国天、南方の増長天、西方の広目天、北方の多聞天が有名で、この中の多聞天は単独で 尊崇される時には毘沙門天と呼ばれます。 このほかにも大黒天や弁財天、帝釈天や梵天などがおられ、お釈迦さまに付き添い、お釈迦さま の法を説く手助けをしたり、仏国土や国家を鎮護したりと様々な特徴があります。
平成27年度 北陸仏青 回答
Q お寺に参拝して御朱印をもらいますが、御朱印ってなんですか?
御朱印とは、もともと参拝者が写経を納めた証としていただく印でした。
それがいつの頃からか納経しなくても参拝のあかしとしていただけるようになり、それが段々と神社にも広 がり今では多くの寺社でいただけるようになりました。 現在ではどなたでも御朱印をいただくことができますが御朱印とスタンプとの違いは寺社の僧侶や職員、神職が押印し、押印と一緒に墨書で寺社名や参拝日、ご本尊名やお堂名を記すことです。
御朱印は寺社名が入っていることから、寺社で授与されるお札などと同等とされ、粗末に扱うべきではないとされています。実際、朱印帳を普段は神棚や仏壇に上げているという人も少なくありません。 御朱印はその時々で頂ける唯一無二のものなのです。
千差万別の筆遣いや印を見返して、訪れたときの光景を思い出すのが楽しいという方も多いようです。
平成27年度 信越仏青 回答
Q 大般若転読法要というのに参加しましたが、大般若経とはどんなお経ですか?
「大般若経」の実名は「大般若波羅蜜多経」と言われ、総数六百巻にも及ぶ大経典群です。
「西遊記」は三蔵法師がお供を連れて、遠く天竺(インド)までありがたい経典を仏さまに頂きに向かう お話ですが、その三蔵法師のモデルとなった玄奘三蔵は、この経典群を中国に持ち帰ると同時に翻訳(インドの言葉から漢訳)を行い、この経典を完成させました。六百巻という膨大な翻訳作業は、相当な苦労が伴っ たことでしょう。
この経典の内容としては、主に「空(くう)」の思想について説かれております。その「空」について端的 に説明することはとても難しいのですが、「あなたの心が、身の回りに起こる事柄で揺れ動き、そこから起 こる感情は良いも悪いもなく幻であるのです。その幻に捉われることのない心を保ち、日々を過ごしましょ う。」といった思想が含まれていると言えるのではないでしょうか。 また余談ではありますが、この六百巻に及ぶ内容のエッセンス(心)を抽出しまとめたものが、われわれ の生活にも身近に説かれる「般若心経」となっているという説もあります。
平成27年度 東京仏青 回答
Q 十三仏の掛け軸を見ましたが、十三仏とはなんですか?
初七日から三十三回忌までの追善供養を司る仏菩薩様が十三体いらっしゃることから派生した信仰で、 この仏菩薩様が姿を変えて亡くなった方々の裁判を行うと言われております。以下、初七日から三十三回忌 までの仏様を表にしました。ご覧ください。
回忌の際はその仏菩薩様に祈念すると故人様の仏果が増すと言われております。
| 回忌 | 十三仏 |
| 初七日 | 不動明王 |
| 二七日 | 釈迦如来 |
| 三七日 | 文殊菩薩 |
| 四七日 | 普賢菩薩 |
| 五七日 | 地蔵菩薩 |
| 六七日 | 弥勒菩薩 |
| 七七日(四十九日) | 薬師如来 |
| 百箇日 | 観音菩薩 |
| 一周忌 | 勢至菩薩 |
| 三回忌 | 阿弥陀如来 |
| 七回忌 | 阿閦如来 |
| 十三回忌 | 大日如来 |
| 三十三回忌 | 虚空蔵菩薩 |
平成27年度 北総仏青 回答
Q お盆での仏壇や盆棚のお祀りの仕方を教えてください。
お盆には、ご先祖があの世から帰って来られる御霊(みたま)・精霊(しょうれい)をお迎えする為に、精霊 棚・盆棚を飾ります。飾り方は、地方、地域、家々などによって風習や習慣が伝えられており、多種多様で すので、ここでは一般的な一つの例を挙げさせて頂きます。
まずお仏壇の扉を開け、お仏壇の前に精霊棚となる小机を置き、マコモで編んだムシロ・盆ゴザを敷き、笹 竹を四隅に立て、縄で結び、ホオズキや五如来旗を吊るし、結界を張ります。次に、お仏壇からお位牌を取 り出し、精霊棚の奥の中央に置きます。香、花、灯明等もお仏壇から出します。季節の野菜、果物、故人の 好物等と、キュウリとナスに麻がらや割りばしで足を作り、キュウリの馬、ナスの牛をお供えします。ご先 祖の精霊に、来る時は馬に乗って早く来てください、牛に乗ってゆっくりお帰りくださいという気持ちが込 められています。
現在では、様々な家の事情により、小机のみで簡略化しているところも多いのですが、おもてなしの心を もって、ご先祖の精霊をお迎えし、ご供養するという気持ちが大切なのです。
平成27年度 埼玉仏青 回答
Q 天台宗のお坊さんは坊主頭でないといけないのですか?なぜ坊主頭なのですか?
現在では高校球児やお坊さんではなくても坊主頭にしている方をよく見かけますが、坊主頭にしている方 になぜ髪の毛を短く丸刈りにしているのか?と質問すると、皆さん「朝起きて髪型に時間がかかったり流行 の髪型を真似したりすることに疲れたから短くしている」と答えます。
そこでお坊さんは、髪の毛に関する悩みを捨て修行に専念するために、坊主頭にしているのです。 天台宗だけでなく他の宗派でも同様の理由から髪の毛を剃り坊主頭にしています。一方で、ある宗ではお坊 さんでもあり大衆でもありと、どちらにも偏らない中間の立場であるという考えから、あえて髪の毛を剃ら ない長髪のお坊さんもいらっしゃいます。
平成27年度 群馬仏青 回答
Q お彼岸(ひがん)とはなんですか?どんな意味でしょうか?
お彼岸は3月の「春分の日」と9月の「秋分の日」の前後3日間、計7日間あり、ご先祖様や自然に感謝し、 悟りの世界に行けるように修行をする期間で、日本独特の仏教行事です。
彼岸は「彼の岸」(悟りの世界)を表わす言葉で、その悟りの世界に到達した状態を「到彼岸」といいま す。彼の岸に到達するための修行方法が「波羅蜜多」であり、波羅蜜多は「パーラミタ―」というインドの 言葉を音写したものです。修行をして穏やかな気持ちになることが悟りの世界へ到達するための第一歩とな ります。お彼岸の初日は「彼岸の入り」、最終日は「彼岸明け」、春分の日・秋分の日は「中日」とよびます。修行ですので「修行に入る」で「彼岸の入り」、「修行が明ける」で「彼岸明け」となります。
仏教には様々 な修行がありますが、お墓参りをしてご先祖様に供養の心を捧げることも、自身を穏やかな気持ちにするた めの修行といえるでしょう。
平成27年度 茨城仏青 回答
Q 天台宗には門跡寺院があると聞いたのですが、門跡ってなんでしょうか?また、門跡はどこの寺院を指し て言うのでしょうか?
門跡とは、一門一派の法跡の意で、元来は、祖師から弟子へと継承されていく宗門の教えのことを、または その伝統の継承者のことをいいます。しかし、899年(昌泰2)に宇多上皇が出家して法皇となり仁和寺に 入ってからは、後世にこれを御門跡と称したために、法皇や法親王が住持したり開創した寺院、またはその住持を御門跡または門主と呼ぶようになりました。
のちには皇族だけでなく貴族についても公卿門跡ができ、室町時代には門跡という語はこうした皇族・貴族のかかわる特定寺院の格式を表す語となりました。 室町幕府は門跡奉行を置いて門跡寺院の政務をつかさどり、江戸幕府は門跡を宮門跡、摂家門跡、清華門跡、准門跡に区別してこれを制度化しました。ところが明治政府により、一時的に門跡と名乗ることをやめ させられることになります。しかし、後になって当時現存する寺院に限って、これを名乗ることを再び許され、現在に至っています。
門跡寺院は、天台、真言、法相、浄土、真宗などの各宗にわたってありますが、たとえば天台宗では八家あり、天台宗の門跡寺院としては、宮門跡として輪王寺(東叡山と日光山)、寛永寺、妙法院、青蓮院、毘沙門堂、三千院、曼殊院、滋賀院という八つの門跡寺院があります。また特に妙法院、青蓮院、毘沙門堂、三千院、曼殊院を「天台五門跡」あるいは「京都五箇室門跡」などといいます。また青蓮院、妙法院、三千院 の三門跡の住持は叡山の座主を兼職したところから「叡山の三門跡」といいます。
平成27年度 栃木仏青 回答
Q 海外にも天台宗寺院はあるのですか?あるならどこにあり、寺院名はなんというのですか?
海外にも天台宗の寺院は4カ所存在しています。アメリカ合衆国に3カ所・インド共和国に1カ所です。 簡単な紹介文とホームページを持っている御寺院は掲載しておきますので、閲覧してみて下さい。
1・天台宗ニューヨーク別院 慈雲山天台寺
アメリカ合衆国ニューヨーク州
毎週水曜日に ウィークリー瞑想サービス(WMS)が行われているようです。ほかにも各月に行事やイベントが開かれているようです。
http://www.tendai.org
2・天台宗ハワイ別院
アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市 毎月第一日曜日には護摩祈祷、第一・第三火曜には絵手紙教室など年間を通して様々な行事を行っているようです。
下記のアドレスは荒了寛御住職のホームページのアドレスです。 http://www.tendaihawaii.org/index.html
3・パロロ観音寺
アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市 2015年、パロロ観音寺80周年の記念法要が執り行われました。日本からも沢山の僧侶のかたが法要に出席し、いけばな光風流家元による献華なども行われ盛大に 80周年の記念法要が円成されたようです。
4・禅定林
インド共和国マハラシュトラ州
平成27年度 福島仏青 回答
Q 天台宗僧侶になるためには何をすれば、どうすればなれますか?
ご質問者様は一般のご家庭(在家)の方とお見受けします。そうであれば、天台宗の僧侶になるには、まず ご自身の師僧となって下さる天台宗の僧侶を見つけなければなりません。基本的には、この師僧にあたる人 物から僧侶としての立ち居振る舞い、心構え等を学んでいくことになります。
そして、師僧に僧侶になることを認められて初めて得度式と言われる式を受け、髪を剃りお釈迦様の弟子となり仏道を歩んでいく誓いをたてます。その後、比叡山に登り本格的な修行の段階へと入ることが許されま す。
そして、比叡山では様々な修行を通して天台僧としての基礎的な教義や法要での作法等を身につけます。これらの行を無事修めて初めて、正式な天台僧としての一歩となります。
平成27年度 陸奥仏青 回答
Q 他の宗派のお坊さんと交流はありますか?
全国的に言いますと全日本仏教会や全日本仏教青年連盟という組織があり、これらに属している宗派は、奈良の東大寺で花祭り法要を行ったり、ネパールなどに行き学校を建てたりと支援活動などで交流をする機会 があります。また、地方においては各自治体などに仏教会があり、勉強会や托鉢等で交流を深めております。
平成27年度 山形仏青 回答